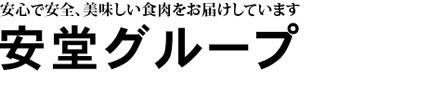安堂グループの歴史物語[第30話]

高森牛の歴史は明治初期に遡ります。その長い歴史のなか、山口県東部随一の牛肉生産を誇る安堂の名が登場するのは、意外にも戦後間もなく、昭和22年のことでした。
これは、現在の安堂グループに至る道のりを辿った歴史物語。そこには、激動の時代を生きた5つの世代、それぞれの苦難と歓喜の秘話がありました。
第30話
「熟成肉、生みの苦しみ」
赤身の肉を劇的に柔らかく美味しくする技術・ドライエイジングによる熟成肉に感激した安堂卓也(現社長)は、早速、それを取り入れることにしました。その技法の日本での第一人者「さの萬」代表の佐野佳治さんの好意により熟成庫を見学した卓也は、それと同じ環境を整えるために工夫を重ね、自社製の熟成庫を完成させました。
ところが、熟成肉独特の香りと赤身の柔らかさは、そう簡単に作れるものではありません。肉塊の熟成を待っても、「さの萬」で見た肉塊のようにカビをまとった熟成肉にはならず、卓也の試みはそこで頓挫していました。
さの萬からの冷蔵便
初めて熟成肉を口にしてから3ヶ月が過ぎようとしていました。
「早く、あの味をうちで作ってみたい」。卓也は焦りにも似た気持ちを抱いていました。
そんな11月上旬、「さの萬」から一箱の冷蔵便が卓也のもとに届きました。そのなかには一つの肉塊。色々な色のカビが表面に付着したままの熟成肉でした。これだけのカビがついた肉塊を見るのは、卓也にとっても初めてのことでした。
実は、「さの萬」の熟成肉を見学した後、卓也は無角和種(経産牛)の肉隗を佐野社長へ送っていたのです。無角和種が熟成肉になったら、いったいどんな肉に変わるのかと、佐野社長も卓也も興味津々でした。佐野社長は1頭分(2本)の骨付きサーロインを安堂畜産に発注し、卓也はそれにもう1本加えて、「これも熟成肉にして、送り返して欲しい」と依頼していました。自分も含めて、父やたくさんの無角和種の関係者に、それを味わって欲しいと考えたからです。
肉塊を見ているうち、卓也に一つの考えが浮かびました。
「このカビをうちの熟成庫に入れたら、どうなるんだろう」。
卓也はカビが付着したロースの両端を削ぐと、熟成庫に置きました。自作の熟成庫のなか、そのカビと安堂畜産の肉塊がどうなっていくのか、期待を膨らませながら…。
その数日後、「さの萬」製の無角和種サーロインを試食する会が開催されました。
熟成肉のガチンコ勝負
2016年11月11日、安堂グループの直営レストラン・高森亭には無角和種に関係する人たちや、安堂畜産の取引先の人たちで満員になっていました。卓也が佐野社長に頼んで熟成肉にしてもらった無角和種のサーロインがお披露目される日が来たのです。
肉は出産の役目を終えた経産牛のもの。人間なら70~80歳のおばあさん牛といったところ。一般に肉質は固く、筋も多く、そのままでは商品価値の乏しいものです。それがドライエイジング(以下、ドライ)によって、どんな肉に生まれ変わるのか。卓也や光明はもちろん、山口県の無角和種の関係者(県の畜産課や無角和種振興公社)にとっても未知でした。
まずは、生肉のお披露目です。比較できるようにと、全く同じ個体のサーロインで、別に真空パックして冷蔵保存していた肉も提示されました。こちらはいわば、乾燥させていないウェットエイジング(以下、ウェット)です。
まず生肉の見た目の違いに、参加者は気付きました。ドライは切ったときの表面がさらっとしていて、赤色に深みがあります。
「これはまるで、マグロの切り身じゃ!」と、一人が声を上げました。
一方、ウェットの方はというと、肉の水分(ドリップ)が出ていて、赤色も浅い印象です。
「ちょっと、焼く前に生肉の匂いを嗅いでみてください」と卓也に促されて、参加者は肉に鼻を近づけました。
「えっ、!? これは…、なんだか独特な香りがしますねぇ」。
「はい、これが熟成肉特有のナッツの香りです」と卓也。
参加者たちは、我も我もと肉を嗅ぎ、その香りを確かめました。
 ▲赤色が深いドライエイジングによる熟成肉
▲赤色が深いドライエイジングによる熟成肉
 ▲香りをかぐ参加者。ナッツの香りに驚きました。
▲香りをかぐ参加者。ナッツの香りに驚きました。
そして、いよいよ実食の時を迎えました。
「えーっ! 何これー!」。各テーブルから驚きの声が上がります。
 ▲焼き上がったドライエイジングによる熟成肉
▲焼き上がったドライエイジングによる熟成肉
実は光明(現・会長)にとっても、熟成肉を食べるのは初めての経験でした。その柔らかさと味わいに驚き、すぐには言葉が出ません。正直、経産牛のサーロインを美味しいと感じたことなどなかった光明です。食べ比べてみればなおさらのことでした。
「こんなことがあり得るのか!?」と、思わずつぶやいていました。
驚きに満ちた店内で、卓也はこっそりガッツポーズをしていました。
「よーし、今度は安堂製の熟成肉を世に出す番だ!」。
安堂製熟成肉、第一号
卓也が工夫して作った熟成庫で、肉塊はカビをまとい、熟成を重ねていました。「さの萬」から送られてきた肉を参考に、どこまでカビが付着すればいいのかを確認しながら、卓也は熟成を待ちました。そして40日が経過して、いよいよその出来栄えを確かめるときが来ました。
カビが付着した表面を慎重にそぎ落とし、あのナッツの香りを期待して鼻を近づけた時のことでした。卓也はすぐに異変に気付きました。
「えっ!? これは…」。
「さの萬」の熟成肉の香りとは明らかに違うのです。
その匂いとは、木材臭。熟成庫の調湿効果を狙って壁に敷いた木材の匂いでした。焼いてみて立ち上がる香りもやはり、あの香ばしいナッツとは違う。食べてみても、どうしても違和感がぬぐえません。木材の香りが強くて、ナッツの香りが消されてしまったのです。
肩を落とす卓也。
考えてみれば、木材の匂いは最初から熟成庫に充満していました。しかし、これほどまでに匂いが付着するとは…、卓也にも想像ができませんでした。
卓也は途方に暮れながらも、何か打開策はないものかと、思案し始めました。
安堂家の性分
安堂畜産の歴史は、時代に翻弄されながらも、それにいち早く対応しようとするトライアルの歴史でもあります。
戦後の混乱期に家畜商から身を起こした初代・安堂寿(第2話)は、肉の産地として既に名を馳せていた高森の地にあって、後発組としての辛酸をなめてきました。あえて困難な遠方への正肉の卸を実現できたのは、その障壁を乗り越えようとしたからです。そして、当時、始まったばかりだった国産ハムの開発にも挑戦し、商品化に成功しています。
2代目の親之(第3話)の時代になると、牛肉の需要が飛躍的に伸びるのをいち早く察知。農家のやる気を引き出して、牛を大きく育ててもらう「肉牛の預託制度」を地域に先駆けて制度化し、肉牛の安定供給を受けて業績を伸ばしました。また、親之の弟・繁美(第3話)は、乳製品への需要の高まりを予見して、地域の農家へ乳牛を斡旋し、その普及に貢献しています。さらに、「いろり山賊」(第4話)と組んで、皇牛というブランドを開発し、現在の人気店の礎を築きました。
3代目の光明(第11話)の時代になると安堂畜産の成長はさらに加速しました。スーパーマーケットの台頭を肌で感じた光明は、人気の部位への需要の集中を予見。それまでの一頭や半頭単位の販売に限界を感じ、畑違いの豚肉の販売業者に学んで、部位別に卸す仕組みを、地域に先駆けて導入しています。また、産地としての生き残りに危機感を覚え、玖西食肉研究会の発起に尽力。産地のシンボルとなる「高森牛」(第14話)ブランドの立ち上げを先頭に立って進めました。
安堂畜産の歴史は、時代の先へ先へと走り続けた歴史です。一つの壁を乗り越えても、決して安穏とすることなく、さらに先を目指す。それは当初、後発組というハンディを乗り越えるために避けられない道でした。しかし、名実ともに地域で一番の食肉業者となってもなお、その姿勢は変わることはありませんでした。4代目の卓也(第21話)もまた、時代の先へと走り続けています。その姿勢は安堂家の性分だと言ってもいいでしょう。
熟成庫に必要な条件の内、温度と風はクリアできても、調湿で躓いた卓也は、ずっと木材に代わる何かを探していました。
そんなある日、卓也は肉牛を解体した後、廃棄されるのを待っている牛の骨を見て、ふと、思いついたのです。しっとりと水分を含んだ肩甲骨の山…。
「あっ、骨は濡れているし、乾きもする…」。
思い立ったら行動あるのみ。卓也は、周囲の目もはばからず、骨を集め始めました。