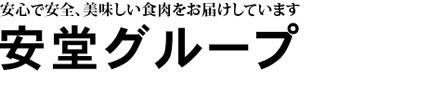安堂グループの歴史物語[第31話]

高森牛の歴史は明治初期に遡ります。その長い歴史のなか、山口県東部随一の牛肉生産を誇る安堂の名が登場するのは、意外にも戦後間もなく、昭和22年のことでした。
これは、現在の安堂グループに至る道のりを辿った歴史物語。そこには、激動の時代を生きた5つの世代、それぞれの苦難と歓喜の秘話がありました。
第31話
「本場アメリカで食べた熟成肉」
一般に、筋が多くて美味しくないとされてきた経産牛(出産の役目を終えた雌牛)の、しかもサシの入らない赤身の肉が、劇的に柔らかくて美味しい料理になる。そんな、ドライエイジングによる熟成肉の美味しさが、高森亭(安堂グループ直営レストラン)での試食会(2016年11月)でも証明され、安堂卓也(現社長)はさらに商品化への意欲を燃やしていました。
しかし、見よう見まねで整備した熟成庫では、ドライエイジングの熟成肉が持つ独特なナッツの香りを再現することはできませんでした。熟成庫の湿度を調節するために敷き詰めた木材の匂いが邪魔をしたからです。木材に代わる調湿材はないものかと、探していた卓也に、ある妙案が浮かびました。
骨を運び始めた社長
卓也が注目したのは牛の骨でした。
牧場から精肉の販売まで一貫して手掛ける安堂グループには、様々な副産物が否応なく発生します。毎日、牛舎から排出されるおびただしい量の牛糞に始まり、脱骨したあとに積まれる骨の山、加工現場で切り出される筋や余分な脂身など…。牛糞は肥料に加工されて地域の農業に貢献し、肉牛の飼料米の栽培にも使われています。
肉から離したばかりの骨はたっぷり水分を含んでいます。表面はつるつるに見えますが、そこには小さな穴があり、内部のスポンジ状の海綿質にもつながっています。つまり、木材と同じように、水分を蓄えたり吸収したりすることができるということ。しかも、同じ牛の体内にあったものです。木材のような異質な匂いとも無縁です。
卓也は、廃棄するために積まれている肩甲骨の山から骨をバスケット一杯に積むと、熟成庫に運び込みました。何だか楽しそうに骨を運び込んでいる様子を見て従業員たちは唖然とし、「社長はいったい、何を考えているのか」とすぐには理解できなかったようです。
ナッツの香り立つ
熟成庫の湿度計からスマホに送られてくる数値を一時間毎に確認する日々が続きました。湿度が下がれば熟成庫に積んだ骨を足し、湿度が上がり過ぎれば除湿器を稼働させます。特に不安だったのは、卓也がモニターを見ることのできない夜から朝にかけての変化です。しかし、骨を使ってからは、湿度変化はずいぶんと緩やかになりました。そして、一週間もしたころには、骨を補充したり、除湿器を稼働させるタイミングも把握し、それが近づくと「そろそろ、骨を用意しておいてくれ」と加工場に連絡し、現場が慌てることもなくなりました。
こうして熟成に必要な40日が過ぎて、安堂畜産初となるドライエイジングによる熟成肉が完成しました。肉の香りはすぐにわかりました。「さの萬」のそれと同じ、あのナッツの香りでした。
仕上がった熟成肉を、卓也は早速、お世話になった「さの萬」の佐野社長へ送りました。すると、
「ああ、いいんじゃないか。それにしても、こんなに早く、よくできましたね」とのこと。
一安心した卓也でしたが、一つのハードルを乗り越えると、また次のハードルが見えてきました。それは、本場アメリカの熟成肉です。「さの萬」の熟成肉は知っていても、本場のそれは見たことも食べたこともありません。だから卓也は、自家製の熟成肉が「これでいいのだ!」という確信が、今一つ持てないでいました。
このことを佐野社長に話すと、こんな提案がありました。
「だったら、一緒にアメリカに行ってみませんか?」。
ニューヨーク、肉三昧の旅
2017年6月22日、卓也はニューヨークに降り立ちました。「NYドライエイジングビーフ2017視察ツアー」と題したその旅行はすでに7回目。主催は、卓也が初めて熟成肉と出合ったあのイベントと同じ日本ドライエイジングビーフ普及協会。佐野社長はその副会長を務めています。
卓也は職業柄、全国各地の肉処で食事をしてきました。高級ステーキ店はもちろん、地元の人がこっそり教えてくれる隠れ家的な店まで…。しかし、このツアーは、そんな体験を吹き飛ばすほどの驚きに満ちていました。
ニューヨークの高級住宅地にある「ブライアント&クーパー」は、自店に熟成庫を併設する名門ステーキハウスです。テーブルに出てきたのは、見たことのない大きな骨付きステーキ。もちろんドライエイジングによる熟成肉です。きれいに骨から切り離され、カットしてありますが、その一枚が日本のステーキと同じ大きさなのです。そして、特有のナッツの強い香りが食欲をそそりました。
 ▲Bryant & Cooper Steak House/ブライアントアンドクーパーのステーキ
▲Bryant & Cooper Steak House/ブライアントアンドクーパーのステーキ ▲お店の方にお話しを伺いました。
▲お店の方にお話しを伺いました。
味わえば、外側はカリカリしていて香ばしく、内側は鮮やかなピンク色で柔らかく、噛めば噛むほど深い味わいが口いっぱいに広がります。これを赤ワインと共にいただけば、他にも何もいらない。そんな幸せな気持ちになりました。
調理法はというと、800℃から1000℃のオーブンで表面をカリッと焼くのだとか。特別な設備がなければ真似のできない方法でした。
肉はアメリカでは定番のアバディーン・アンガス牛。黒毛和牛よりも体格が大きく、肉質は柔らかく、サシの入らない赤身が特徴です。肉に含まれる水分が多いことから、ドライエイジングの熟成法に適した品種です。
ブルックリンで100年以上続く名門「ピータールーガー」にも行きました。予約を取るのも難しい人気店です。そこの名物はポーターハウスステーキ(Tボーンステーキ)。T字の骨を境にヒレ肉とサーロインの両方が味わえるというもの。その大きさに驚きながら、口に入れれば、やはり赤身肉のうま味が染みわたります。ここでもやはり、大きなステーキもぺろりと平らげました。黒毛和牛の霜降り肉では、途中で飽きて、とてもその量は食べ切れなかったでしょう。

▲Peter Luger Steak House/ピータールーガーの外観
 ▲Peter Luger Steak HouseのTボーンステーキ
▲Peter Luger Steak HouseのTボーンステーキ ▲Katz’s Delicatessen/カッツデリカッセンのパストラミサンドイッチ
▲Katz’s Delicatessen/カッツデリカッセンのパストラミサンドイッチ
パストラミと言えばぱさぱさした感じですが、ここのパストラミはしっとり柔らかくて美味しい。牛のカタバラは本来、硬い部位なのに…、熟成肉以外でも、感動の度でした。
ツアーは、なんと一日三食ステーキというあり得ない設定でしたが、どこのレストランでも赤ワイン片手に、肉三昧を楽しみました。そして、「いったいどんな熟成庫で作られるのか?」という好奇心が、どんどん膨らみました。
意外な熟成管理
いよいよ熟成工場の視察にやってきた卓也は、意外にラフな作業風景に開いた口がふさがりませんでした。厳密な温度・湿度管理や、風の当て方など、神経を擦り減らして工夫を重ねた卓也でしたが、ここでは「おおざっぱ」という言葉がぴったりでした。
大型の扇風機を肉塊に当て、時々、その扇風機の位置を変えたりする。湿度もだいたいこのくらい。乾き具合も、厳密な管理などありません。カビも生えていたりいなかったり。そこで卓也は気付きました。
「そうか、日本人は細かいことを気にし過ぎなのかもしれない。綺麗にカビを生やすことに懸命だけど、本当はそれが目的じゃない。美味しい熟成肉になればそれでいい」。
後から分かったことですが、カビは香り付けには重要な役割を果たしますが、肉の熟成度合いや味わいにはあまり影響はしないようです。だから、アメリカのようなラフな管理でもちゃんと美味しい熟成肉ができるのです。
「じゃあ肉の味の違いは…、いったいどこから来るのだろう?」。
熟成肉の探求は続く
アメリカから帰国して、卓也は自社製の熟成肉を食べながら考えました。そして、行きついた答えの一つが、肉牛そのものの違いでした。
アンガス牛なら同じ味の熟成肉を作ることができるでしょう。しかし、アンガス牛を安堂畜産の牛舎で肥育するのには無理があります。体が大きすぎて、牛舎がもたないし、アメリカ産の熟成肉と同じものを作っても、仕方がない。
卓也はその後、様々な肉で熟成肉を試作し始めました。アンガス牛の血が入っている無角和種は美味しい熟成肉になると分かっていますが、頭数があまりにも少ない。そこで、熊本の褐毛和種(あかげわしゅ)や、乳牛が主なホルスタインやジャージー牛も試してみました。なかでも、ジャージー牛はドライエイジングに合うことが確認できました。ところがこれも数が少ないのと、肥育しても大きくならないという難点があります。
2017年5月から安堂畜産製の熟成肉は店頭に並んでいます。「これを食べたら、他が食べられない!」というコアなファンも現れています。幾つかのレストランからも注文が入り、その取引は2020年の現在も継続しています。そして、卓也の「アメリカのそれに負けないもっと美味しい熟成肉を」という探求もまた、続いています。
縦の糸と横の糸
安堂グループは熟成肉の商品化に成功することにより、類まれな食肉事業者になりました。菌数を極限まで抑えた生食(牛タタキ)を製造しながら、40日間もカビを生やして熟成させる熟成肉を製造しています。この両極端とその間にある通常の精肉販売、その全ての商品ラインを製造・販売する事業体は、日本全国を探しても安堂グループ以外には見当たりません。
さらに、肉牛の繁殖から精肉販売・レストラン経営という、川上から川下までを一貫して行う事業体もまた、稀です。
川上から川下が縦の糸なら、広い商品ラインは横の糸。紡ぐのは…どんな流通業者や消費者のニーズにも応えることのできる幅広い布。どのように消費ニーズが変化しようとも、カバーすることのできる幅広い布が、ここに完成したのです。
さて、美味しい熟成肉への鍵の一つが牛の品種であるように、品種の保存・改良は食肉事業者にとって、いつの時代も最大の関心事です。また、上述の広い布に例えれば、品種は糸の素材そのものと言っていいでしょう。
物語は、安堂グループが守り育てようとする品種の話へと進みます。